FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/27 は
スッキリわかる FP技能士3級
第5章 「不動産」
を読みました
読んだ内容は
- 不動産に関する法律
です
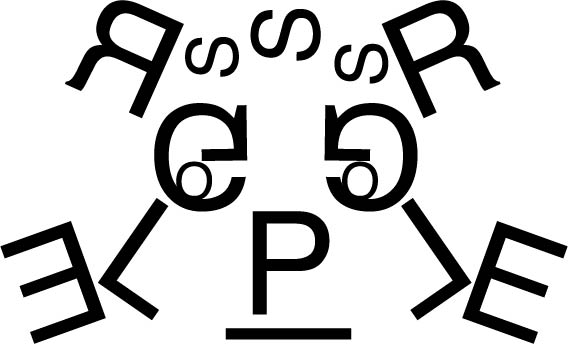
不動産に関する法律
都市計画法
計画的に街づくりを進めることを都市計画
その内容や手続き、開発許可などの規制を定めたものが
都市計画法という
都市計画区域
都市計画区域は「都市計画区域」「時計画区域外」
にわかられる
「都市計画区域」の指定は
→ 都道府県が行う
→ 複数の都府県にまたがる場合は
国土交通大臣が行う
| 市街化区域 | 既に市街地を成形している地域 および 10年以内に 優先的・計画的に市街化を図るべき区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべきものとして指定されている区域 |
| 非線引区域 | 市街化区域と市街化調査区域 |
用途地域
市街化区域内に定められる地域
都市全体の土地利用の基本的な枠組みを設定
「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれている
開発許可制度
開発行為 → 建築物等ってるために行う土地の造成など
都市計画地域・準都市計画地域内で開発行為を行うには
「都道府県知事の許可が必要」
ただし 下の場合は許可は不要
→ 市街化区域内1000㎡未満の開発行為
→ 非線引の都市計画区域内で行う3000㎡未満の開発行為
→ 市街化調整区域内で行う農林漁業用建築など
公共的施設(鉄道施設・公民館)公共事業などや非常災害の応急措置
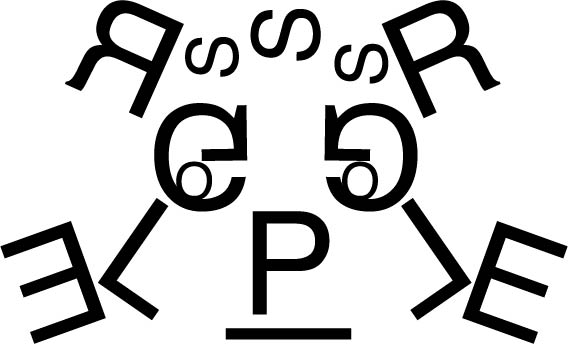
建築基準法
建築基準法の中で
「道路に関する規制」「建蔽率と許容率」について
「道路に関する規制」
1)建築基準法上の道路
道幅が4m以上 ただし
法ができる前に道路として機能していれば
道路の中心から2m後退した線が道路の境界線
2)接道義務
都市計画区域内 準都市計画区域内の建物の敷地は
道路に2m以上接していないといけない
1)2)はどちらも消防車が入りやすくするためのようです
「建蔽率と許容率」
1)建蔽率
敷地面積に対する建築面積(≒真上から見たときの面積)
30~80%まで認められるが以下の条件を満たすと緩和できる
| 条件 | 緩和率 |
|---|---|
| 特定行政庁が指定する角地 | 10%緩和 |
| 防火地域・準防火地域にある 耐火建築物 | 10%緩和 |
| 上の両方に該当する | 20%緩和 |
| 建蔽率が80の地域で 防災地域内になる耐火建築物 | 建蔽率制限なし |
2)容積率
敷地面積に対する建物の延床面積の割合
敷地の前面道路の道幅次第で容積率が変化する
道幅12m以上は用途地域に定められている指定容量率
道幅12m未満は下表の乗数をかけたものと
指定容量率を比較して厳しい方が適応
| 地域 | 乗数 |
|---|---|
| 住宅系用途地域 | 0.4 |
| 住宅系用途地域以外 | 0.6 |
敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は
過半の属する地域の制限
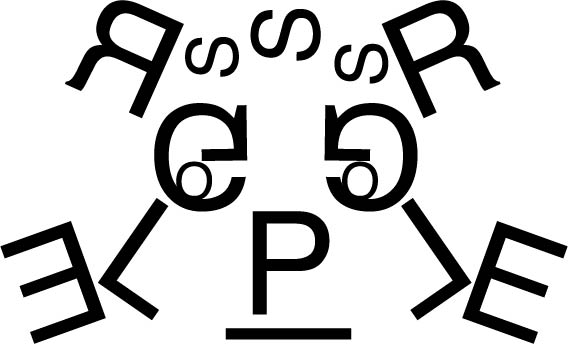
明日は これ以降の
第5章 不動産 に進む予定です
スポンサーリンク








